MENU
MENU
『青淵』No.847 2019(平成31)年10月号
渋沢栄一の没後50年以上が経過した1988(昭和63)年に、「'88 さいたま博覧会」が開催されました。今から約30年も前のことですが、ご記憶のある方や、実際に会場を訪れた方もいらっしゃるでしょう。
「自由―躍動する未来の創造」をテーマとして、さいたま博覧会実行委員会が主催、渋沢栄一の生誕地に近い埼玉県熊谷市を会場地として、同年3月19日から5月29日までの会期中に約250万人が来場しました。時代はちょうど「バブル景気」の末期であり、各地で同様の地方博覧会が開催されていました。
広さがおよそ20ヘクタールの会場内には、メインパビリオンの「テーマ館」、開催地の「くまがや館」のほか、「埼玉銀行館」、「東京電力館」、「東芝館」など様々なパビリオンが建ち並びました。また「日本初の公開試乗」と銘打たれ、リニア・モーターで走る「リムトレイン」の乗車体験もできました。
さいたま博で注目すべきは、渋沢栄一を伝えるパビリオン「渋沢栄一館」が建てられたことです。埼玉県における郷土の偉人・渋沢栄一の足跡を「あらゆる角度から展示紹介し、その進取の気性・先見力・創造力・ダイナミックなパワー等に触れ、未来への指針」とすることが大きなテーマとされました(『'88 さいたま博覧会公式記録』)。パビリオンの面積は607平方メートル、第一国立銀行の外観を模した長方形の建物で、さいたま博を代表するパビリオンとして人気を集め、会期中に約29万人が入館しました。
このパビリオンは、さいたま博覧会実行委員会による出展で、当財団が全面的な協力を行ないました。写真をはじめとした当館所蔵資料を提供したほか、展示パネルの解説文、資料キャプションの執筆や資料の展示作業など、当館学芸員が展示制作に関わりました。
館内は4つのエリアで構成されており、展示と映像によって段階的に渋沢栄一の足跡を理解するというものでした。まず来館者を迎えるエントランスゾーン〈ウェルカム晩香廬〉で、晩香廬のインテリアイメージと栄一の貴賓もてなしが再現されました。次に映像ゾーン〈青淵シアター〉では、3面マルチスクリーンで「未来への挑戦」と題した、栄一のドキュメンタリー・ドラマが上映されました。3つめの展示ゾーン〈青淵ホール〉では、実業家としての活動を草創期、黄金期、成熟期、晩期に分けて、栄一の事績と関係資料が展示紹介されました。そしてエンディング〈メッセージホール〉では、「埼玉から世界へ'88 」というテーマで、栄一が関わった日米親善人形の事業を題材とした展示により、栄一の「国際親善」精神が紹介されました。
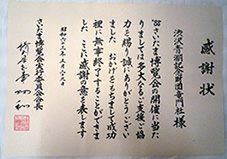
さいたま博覧会実行委員会より当財団に贈呈された「感謝状」
「さいたま博覧会『渋沢栄一館』(仮称)設立にあたって」ほか関係書類
渋沢栄一は1867年のパリ万国博など、実際に国内外、多数の博覧会に関与しましたが、郷土で開催された地方博覧会とはいえ、自分をテーマとしたパビリオンが作られるとは夢にも思わなかったに違いありません。もしも、栄一がさいたま博を訪れたならば、「渋沢栄一館」に対して、どのような談話を発表したのでしょうか。とても興味がわきます。
渋沢史料館には、さいたま博・「渋沢栄一館」にまつわる資料が一括で収蔵されており、当財団・当館がどのような協力をしたのか、当時の状況をうかがい知ることができます。同博覧会「開催趣旨」や「渋沢栄一館」企画案、基本計画、基本設計などの諸資料を見ていくと、元号が昭和から平成にかわる直前の1988年当時において、渋沢栄一をどのように評価し、展示表現しようとしていたのか、具体的な制作過程とともに当時の雰囲気も伝わってきます。
現在、当館では常設展示等のリニューアルに向けて準備、工事を進めています。「さいたま博」開催時とは社会状況は大きく異なりますが、過去に実施された渋沢栄一の展示から学ぶことも多くあります。「令和」という新しい時代において、あらためて「渋沢栄一」を展示で表現すべく、努力していきたいと思います。
(学芸員 関根 仁)
