MENU
MENU
『青淵』No.811 2016(平成28)年10月号
1867(慶応3)年、渋沢栄一はフランス・パリの地にいました。
この年、15代将軍徳川慶喜の実弟・昭武は将軍名代として、パリで開催される万国博覧会に派遣されました。昭武の随員には、外国奉行の向山隼人正、傅役の山高石見守、医師の高松凌雲、さらに田辺太一、杉浦愛蔵らがいました。このなかで栄一は、約1年半の渡欧中、庶務や経理を担当したのです。
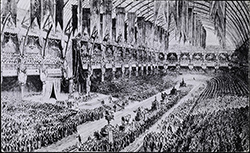
パリ万博の褒賞授与式会場
(『渋沢栄一伝記資料』別巻第10より) 博覧会とは、様々な産物、技術、芸術・文化等を集中展示し、公衆に観覧させる催しのことです。近代博覧会の始まりは、1798年にフランスが国内で開いた博覧会とされ、さらに博覧会の規模を拡大し、国内のみならず国際的な催しに発展させたのが、産業革命を達成したイギリスであり、1851年のロンドン万国博覧会がその最初です。ロンドン万博の成功は他の欧米諸国にも大きな影響を与え、産業の近代化、蒸気船・鉄道など移動手段の発達、ツーリズムなどを背景として、毎年のように各国・各地域で開催されていきました。
フランス皇帝ナポレオン3世は、万国博覧会を「全世界の人々が工業力を競うオリンピックである」と位置付け、さらに自らの権力基盤を固めることに意義を見出しました。
パリ万博の会場は、セーヌ川沿いのシャン・ド・マルス(旧練兵場)。ここにタテ約490メートル、ヨコ約386メートルの巨大な楕円形のパビリオンを建設しました。この建物内は同心円状に仕切られており、最も外側に最新の機械工業、内側に進むにつれて手工業、工芸、美術品が展示され、最も内側には中庭が設置されていました。会場の動力は蒸気力でまかなわれ、欧米出品の最新機械が会場で注目を浴びました。会期中は約1500万人の入場者があり、その後の万博のモデルとなったのです。
パリ万博開催にあたり、駐日仏公使レオン・ロッシュは徳川幕府に万博参加を勧誘。幕府は求めに応じ、公式参加を決定します。さらに諸藩に出品・参加を呼びかけ、幕府、薩摩藩、佐賀藩、そして江戸の商人・瑞穂屋卯三郎が出品をすることとなりました。日本の出品物や、卯三郎が出店した日本茶店は会場で好評を得ました。
徳川昭武一行は万博会場を何度か視察しており、栄一もこれに随行しました。
栄一は実際に見た万博会場の様子を、一橋家家臣の川村恵十郎に宛てた書簡のなかで次のように述べています。「博覧会の展示はほんとうに壮大で素晴らしく、世界中から実用品やそれ以外の品々が出品物として並べられ、それらに驚かされます。日本の出品物の評判は大変良く、鑑定員による品評でも、イギリス、アメリカ、プロイセンなどと同様に最高の賞牌を授与されるとのことであり、国の名誉として喜びの至りです」(『渋沢栄一伝記資料』第1巻より・筆者抄訳)。
栄一は率直に博覧会の盛大さ、そして各国の出品物に驚嘆しているほか、日本の出品物が会場でも評判が良いことを報告したのでした。
パリ万博に因んで、栄一が驚いたことがあります。同年7月1日に万博の褒賞授与式が挙行され、ナポレオン3世が演説を行ないました。その翌朝、演説内容が新聞に報道されて、フランス語を読めない栄一でも翻訳をすれば、その内容を知ることができたのです。栄一はこのときに、新聞が「誠に面白いもので、同時に非常に重宝なものである」と実感したのでした。
来年、2017年はパリ万博が開催され、また栄一が渡仏して150年という節目の年にあたります。
渋沢史料館では現在、これに関連した展覧会やその他の事業などを計画、準備中です。海外に行くことが困難であった当時、万博やパリの街で栄一がどのような体験をしたのかを探っていきたいと考えています。ぜひご期待いただければ幸いです。
(学芸員 関根 仁)
