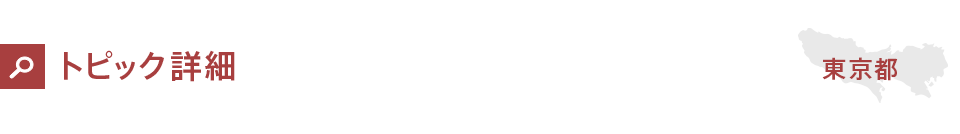[ 解説 ]
1914(大正12)年12月18日、東京駅は開業の日を迎えました。この日は9時から開業式が行われ、その後11時30分からは東京市および東京市有志の発起による開業祝賀会が開催されました。この祝賀会は第一次世界大戦で青島から凱旋した将軍の歓迎式を兼ねて開催されたもので、渋沢栄一は祝賀会発起人代表として挨拶を述べ、次のように語っています。
「東海道五十三次の道中双六に採り同双六に於て江戸を振り出とし京都を上りと為したる道程も、今や我が国運の進歩と世界交通の発達とに依り、東京を起点とし倫敦を上りと為すの盛況に達するに至れり、而して東京駅の建設は実に此の世界的交通の上に最も善美なる設備を与へたるものなり」
(『渋沢栄一伝記資料』第48巻 p.508収載『東京駅開業祝賀会及凱旋将軍歓迎会報告書』(大正4年4月刊)より)
また『渋沢栄一伝記資料』第48巻にはこの日の東京駅の様子が『中外商業新報』からの再録により次のように紹介されています。
「駅前雑踏 燦たる夜の美観
空は一碧拭ふが如くに晴れ冬には珍らしい好天気であつたので、三菱原頭目蒐けて集つた市民の数は驚く程多かつた、神尾将軍の凱旋を迎へた後で一時は帰り行く者の方が多いやうであつたが、正午頃からは
△爺も婆も娘も 孫も東京駅へ東京駅へと押出したので、それこそ全く定り文句通り美しく装飾された三菱ケ原は人を以て埋められた、紅白の巻柱に紅白の幔幕、剰けに色提灯など花々しく吊るした三個の余興場では、一方に犬塚士道門下の剣舞術が始まれば、他では滑稽の隊長鶴屋団十郎一座が大阪式の仁和加を演じ、又一ケ所では
△丸一の大神楽 が「吉例によりまして鞠と撥との綾取りを始めまする」次第でさしもの広場が見物人で一杯となる、此他に花火は止め度もなくボーンボーンと打揚げられるし、鬚達摩主催の素人相撲が亦大に人気を喚ぶし、此処新東京駅前は忽ちにして歓楽の巷に化した、空地といふ空地には香具師や露店が陣取つてこれ又盛に客を喚び
△お濠端の道路 にまで沢山の露店が並ぶ有様である、斯うして其処へ日ねもす押寄せて来る人間が澱みをなし、仰いでは煙火を見、アーチを望み、余興を見物し、殆んど未曾有といふも可い程の賑ひを呈した、殊に夜に入つては此辺一帯イルミネーションの光で白昼の如く、新停車場・大アーチ・緑塔など珠を鏤めたやうな美観を呈したので余興も引続き演ぜられたから、昼にも増した雑踏を呈した」
(『渋沢栄一伝記資料』第48巻 p.512-513収載 『中外商業新報』第10296号(大正3年12月19日)より)
[ 参考リンク ]
▶東京駅100年の記憶〔東京ステーションギャラリー - TOKYO STATION GALLERY - 〕
▶『東京駅開業祝賀会及凱旋将軍歓迎会報告書』p[2] 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕

東京駅開業祝賀会当日の渋沢栄一(国立国会図書館デジタルコレクション『東京駅開業祝賀会及凱旋将軍歓迎会報告書』p[2]より転載)
出典:『渋沢栄一伝記資料』 3編 社会公共事業尽瘁並ニ実業界後援時代 明治四十二年~昭和六年 / 1部 社会公共事業 / 9章 其他ノ公共事業 / 5節 祝賀会・表彰会 / 5款 東京駅開業祝賀会 【第49巻 p.379】