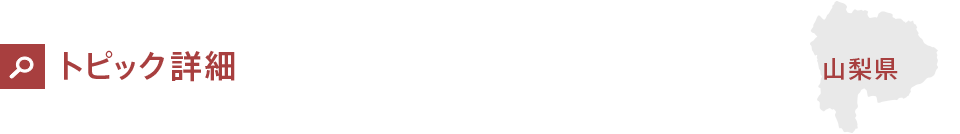[ 解説 ]
山梨県西部から静岡県東部を経由して駿河湾にそそぐ富士川流域には、江戸時代より高瀬舟による舟運が発達していましたが、甲州の水を集める富士川は雨が降ると運輸が途絶し、また水難なども問題となっていました。その対策として甲州の実業家堀内良平(ほりうち・りょうへい、1870-1944)は地元有志らと図り、私設鉄道を富士・身延間に敷設する計画を立てました。
堀内から相談を受けた渋沢栄一は、日蓮上人霊蹟身延山への鉄道敷設は参詣者のためには結構な企画だが、産業開発のため、将来の大計を思えば身延までではなく必ず富士・甲府間とすべき、と進言しました。また、栄一は堀内に静岡や東京の実業家を紹介し、自らも出資するなど会社設立を支援、1912(明治45)年に富士身延鉄道株式会社が成立しました。
その後富士・身延間は1920(大正9)年に開通、1928(昭和3)年には甲府・富士駅間の全通が実現、身延線は東海道線と中央線を結ぶ物流の幹線となりました。
出典:『渋沢栄一伝記資料』 3編 社会公共事業尽瘁並ニ実業界後援時代 明治四十二年~昭和六年 / 2部 実業・経済 / 2章 交通・通信 / 2節 陸運 / 5款 富士身延鉄道株式会社 【第51巻 p.523-534】